犬や猫の寿命が延びるなかで、増加している病気のひとつが「腎臓病(慢性腎臓病・腎不全)」です。特に高齢のペットに多く見られ、進行すると命に関わる重大な疾患です。
本記事では、犬や猫における腎臓病の基礎知識から、具体的な症状、治療法、予防法までをわかりやすくご紹介します。
大切な家族であるペットの健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
この記事の結論
- 腎臓病は完治が難しく、治療と日常ケアで進行を抑える
- 食事療法や内服薬、点滴が主な治療方法として重要
- 水分摂取や適切な食事管理が予防と症状悪化防止に有効
- 定期健診での早期発見が長寿と健康維持の鍵となる
目次
犬や猫に多い腎臓病とは?
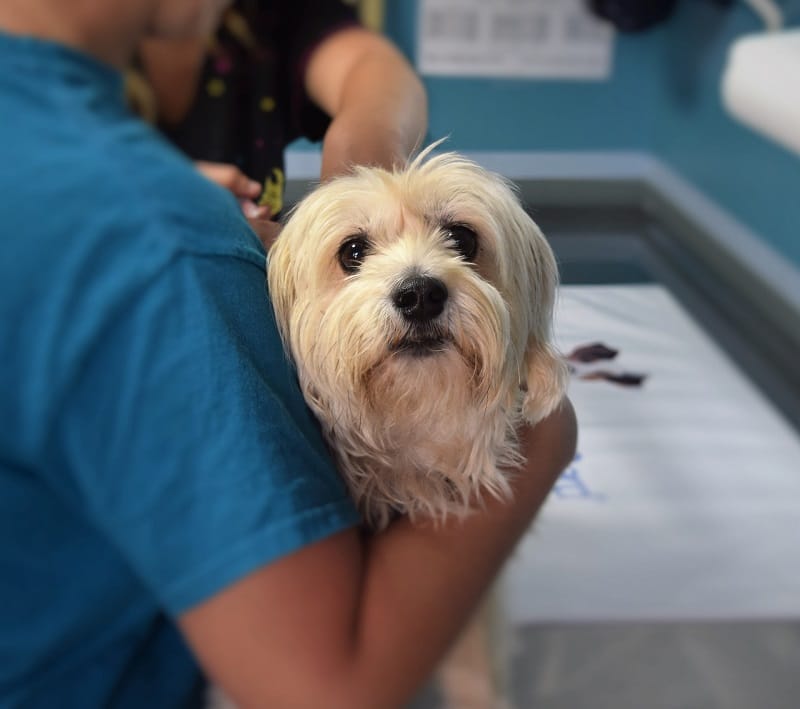
犬や猫に多く見られる腎臓病は、腎臓の機能が徐々に低下する「慢性腎臓病」と、急激に機能が失われる「急性腎不全」に大別されます。
特に高齢のペットにおいて慢性腎臓病の発症率は高く、進行すると体内の老廃物や余分な水分を排出できなくなり、食欲不振や嘔吐、体重減少などの症状が現れます。
腎臓病は初期段階では目立った症状が出にくいため、発見が遅れることが多く、重症化を防ぐには早期発見・早期対応が重要です。
腎臓と免疫の関係とは?
腎臓は老廃物を排出するだけでなく、体内の免疫バランスにも深く関わる臓器です。腎機能が低下すると、体内に毒素が蓄積し、慢性炎症や栄養障害、貧血などが進行。これにより白血球の働きが弱まり、免疫力が下がることが知られています。
特に慢性腎臓病では、感染症への抵抗力が低下しやすく、治療中も注意が必要です。一方で、免疫力が低下したこと自体が直接腎臓病の原因になることは少ないものの、感染症や自己免疫疾患などを通じて腎臓が傷害されるケースもあります。
腎臓と免疫は一方通行ではなく、互いに影響し合う関係にあるため、腎臓病のケアには免疫の視点も欠かせません。
腎臓の役割と腎臓病の定義
腎臓は体内の老廃物や毒素を尿として排出する役割を持ち、水分や電解質のバランスを保ちます。また、血圧調整や赤血球の生成を助けるホルモンの分泌にも関わっています。
腎臓病とは、これらの機能が低下する病態の総称で、特に腎臓のろ過能力が失われることで体内に毒素が蓄積し、全身に悪影響を及ぼします。
残念ながら、腎臓は一度損傷すると再生が難しい臓器であり、早期のケアが健康維持の鍵となります。
慢性腎臓病と急性腎不全の違い
慢性腎臓病(CKD)は数か月から数年にわたり徐々に腎機能が低下していく病気で、特に高齢の犬や猫に多く見られます。
一方、急性腎不全は短期間で腎機能が急激に悪化する病態で、原因には中毒や感染症、外傷などが挙げられます。
慢性腎臓病は初期段階では無症状なことが多く、定期的な血液検査での早期発見が重要です。急性腎不全は治療次第で回復が可能ですが、対応が遅れると命に関わる場合もあります。
高齢になるとリスクが高まる理由
犬や猫も加齢とともに腎臓の細胞が徐々に損傷し、ろ過機能が低下します。加齢による代謝機能の衰えにより、腎臓への血流も減少し、老廃物の処理能力が低下するのが主な要因です。
また、高齢になると水分摂取量が減る傾向にあり、慢性的な脱水状態が腎臓に負担をかけることも少なくありません。
さらに、他の慢性疾患(高血圧や心臓病など)も腎臓に影響を及ぼすため、シニア期の健康管理には特に注意が必要です。
犬猫の腎臓病の検査と診断方法

犬や猫の腎臓病を正しく診断するには、いくつかの検査を組み合わせて総合的に判断することが必要です。
目に見える症状だけでは病気の進行度を判断できないため、血液検査や尿検査、画像診断を通じて腎機能の状態を調べます。
特に早期発見が治療効果を左右するため、異変に気づいたら速やかに動物病院で診察を受けることが大切です。
動物病院で行われる主な検査
腎臓病の診断には、以下のような検査が一般的に行われます。
- 血液検査:腎臓の機能や体内の老廃物の蓄積を数値で確認
- 尿検査:尿の濃さやタンパクの有無を調べる
- 画像診断:腎臓の形や大きさ、結石の有無などを確認
- 血圧測定:腎機能の低下に伴う高血圧のチェック
これらの検査を組み合わせて、腎臓の健康状態や病気の進行度を把握します。
血液検査
血液検査は腎臓病の診断において最も重要な検査のひとつです。腎臓が老廃物をうまく排出できなくなると、血液中の数値に異常が現れます。特に以下の項目が注目されます。
| 項目 | 意味・異常時の影響 |
|---|---|
| BUN(尿素窒素) | 上昇すると腎機能低下の可能性 |
| クレアチニン | 腎臓の濾過機能を反映する指標 |
| SDMA | 早期の腎機能低下を発見できる新しい指標 |
これらの数値から腎臓病の有無や重症度を評価します。
尿検査
尿検査は、腎臓が尿をどのように処理しているかを確認するために行われます。特に尿比重の低下は、尿を濃縮できない腎臓の異常を示すサインです。
また、タンパク尿がある場合は腎臓の糸球体に障害が起きている可能性もあります。
- 尿の濃度(尿比重)
- 尿中のタンパク、血液、糖の有無
- 尿中に含まれる結晶や細胞成分
簡便かつ負担の少ない検査なので、定期的なチェックに適しています。
画像診断(エコー・X線)
画像診断では、腎臓の大きさや形、構造を直接確認できます。
超音波(エコー)検査では、腎臓の内部構造や腫瘍、結石の有無を詳しく観察できます。
X線検査は腎臓の位置や大きさ、カルシウムを含む結石の確認に有効です。
画像検査は痛みを伴わないため、高齢動物にも負担が少なく、進行度や治療方針の判断にも役立ちます。
定期的な健康診断の重要性
腎臓病は進行しないと目立った症状が現れにくいため、定期的な健康診断が早期発見には欠かせません。特に7歳以上の中高齢の犬猫では、半年に1回の検診を推奨します。
初期であれば食事療法などで進行を抑えることも可能なため、以下の項目を含む定期的な検査が理想的です。
- 血液検査(BUN・クレアチニン・SDMAなど)
- 尿検査
- 体重・食欲・水分摂取量のチェック
- 獣医師による触診と問診
健康診断を習慣化することで、大切な家族であるペットの健康寿命を延ばすことができます。
腎臓病の原因とは?犬猫それぞれの要因を解説

犬や猫の腎臓病には、さまざまな原因が関与しています。代表的な要因として「加齢」「遺伝」「感染症」「中毒」「食生活」「脱水」などが挙げられ、動物種や個体差によっても異なります。
犬は遺伝性の疾患や毒物による急性腎障害が比較的多く、猫は加齢に伴う慢性腎臓病が一般的です。
特に猫は水をあまり飲まない性質があるため、慢性的な脱水が腎臓に負担をかけやすくなります。それぞれの原因を正しく理解し、早期対策を行うことが重要です。
犬の腎臓病の主な原因
犬の腎臓病は、主に加齢、遺伝性疾患、感染症、中毒などが原因となります。
高齢犬では長年の腎臓への負担が蓄積されて腎機能が低下するケースが多く見られます。また、特定の犬種においては若齢でも遺伝性の腎疾患が発症することがあります。
さらに、細菌感染やウイルス感染、誤って摂取した中毒物質(ブドウやユリ、特定の薬剤など)も急性腎障害を引き起こす原因となります。原因に応じた早期対応と予防策が大切です。
猫の腎臓病の主な原因
猫は本来、乾燥地帯に住んでいた動物であるため、水分をあまり摂取しない傾向があります。このため、腎臓に常に負担がかかりやすく、慢性腎臓病の発症率が非常に高いです。
さらに、加齢により腎機能が徐々に低下し、食生活や脱水、ストレスなどが進行を早める要因になります。特に7歳を過ぎたあたりから腎機能の衰えが見られることが多く、早期の対策が求められます。
定期的な検査とバランスの取れた食事がカギになります。
犬や猫の腎臓病の主な症状とは?

腎臓病は徐々に進行するため、初期には目立った症状が現れにくいのが特徴です。進行とともに老廃物が体に溜まり、さまざまな不調が現れます。
次のような症状は他の病気でも見られるため、早期の血液検査や尿検査が重要です。特に高齢の犬猫は定期的な健康診断が推奨されます。
初期段階で見られるサイン
腎臓病の初期は「多飲多尿」が最も分かりやすいサインです。これは、腎臓の濾過能力が落ち、尿の濃縮がうまくできなくなるためです。他にも以下のような変化に気づいたら注意が必要です。
- トイレの回数や尿量の増加
- 水を飲む量が明らかに増えた
- 食べる量が減った
- なんとなく元気がない
これらは飼い主であれば比較的気づきやすい変化です。症状が軽いうちに獣医師に相談することで、進行を抑える治療が可能になります。
進行するとどうなる?末期症状のチェックポイント
腎臓病が進行すると、体内に毒素が溜まり全身に影響が出てきます。末期には以下のような深刻な症状が見られます。
| 症状 | 内容 |
|---|---|
| 嘔吐・下痢 | 毒素の蓄積により消化器系が影響を受ける |
| 痙攣 | 尿毒症による神経への影響 |
| 極端な食欲不振 | 毒素による胃の不快感などが原因 |
| 貧血 | 腎臓からのホルモン分泌低下によるもの |
| 無気力・昏睡 | 重度の尿毒症による末期症状 |
この段階になると、延命処置や緩和ケアが中心になります。末期になる前に、早期の対策が重要です。
見逃しやすい症状にも注意
腎臓病は初期に顕著な症状が出にくいため、飼い主が異変に気づかず見逃してしまうことが多いです。以下のような「見逃しやすいサイン」には特に注意しましょう。
- トイレの掃除をしていて尿の量が多いと感じる
- 水飲みの回数が増えているが気づかない
- 毛並みが以前よりボサボサになっている
- 日中ずっと寝ていることが増えた
些細な変化でも、日々の観察で気づけることがあります。気になる行動が続く場合は、早めに動物病院で検査を受けましょう。
犬猫の腎臓病の治療方法と日常ケア

腎臓病の治療は病気の進行を遅らせ、生活の質を保つことが目的です。完治が難しい病気であるため、治療と日常ケアを併用して管理することが大切です。
主な治療法には食事療法や内服薬、皮下点滴があり、病状や進行度によって内容が異なります。飼い主が毎日の生活の中でできるケアも多く、継続的な取り組みが必要です。
食事療法と療法食の役割
腎臓病では食事管理が非常に重要です。療法食には腎臓の負担を軽減するための以下のような工夫がされています。
- 低タンパク:老廃物の生成を抑える
- 低リン:腎機能の悪化を防ぐ
- 高カロリー:食欲が落ちたときにもエネルギー確保が可能
- 抗酸化成分やオメガ3脂肪酸:腎機能の維持に役立つ成分を配合
療法食は市販の一般的なフードとは異なり、これらの特定成分の調整が難しいため、獣医師の指導のもとで専用の療法食を与えることが大切です。療法食は自己判断で選ぶものではなく、必ず獣医師の指示に従ってください。
また、療法食とは別に、食事療法として不足する栄養素や機能性成分をサプリメントで補う方法があります。抗酸化成分やオメガ3脂肪酸、免疫調整作用を持つフアイア糖鎖TPG-1などがこれに該当します。
このように療法食とサプリメントを適切に組み合わせることで、腎臓病に対するより効果的な食事療法が可能になります。具体的な活用方法や選択については、かかりつけの獣医師にご相談ください。
内服薬や点滴治療
腎臓病では、症状や進行度に応じて内服薬や皮下点滴などの治療が行われます。
| 内服薬 | 血圧の安定、タンパク尿の改善、食欲増進などを目的に使用 |
| 皮下点滴(輸液療法) | 脱水や毒素の蓄積を防ぎ、腎臓への負担を軽減 |
| 制酸剤や胃腸薬 | 嘔吐・食欲不振などの症状を緩和 |
これらの治療は病院で行うものもあれば、自宅で継続できるものもあり、日常ケアとの併用が求められます。
在宅ケアでできること
在宅でもできるケアは多く、治療と並行して行うことで生活の質を高められます。以下のような取り組みが有効です。
- 新鮮な水を複数箇所に設置し、飲水量を確保
- 食事は療法食を基本に、食欲に応じた工夫を
- 快適で静かな環境を保つ
- 皮下点滴を獣医の指導のもと自宅で行う場合もある
小さなことの積み重ねが、腎臓の負担軽減につながります。
完治は難しい?治療の目的とは
腎臓病は一度発症すると、腎臓の機能を元に戻すことは非常に困難です。これは腎臓が再生能力をほとんど持たない臓器であるためです。治療の主な目的は以下の通りです。
- 症状の緩和
- 進行の抑制
- 合併症の予防
- 動物のQOL(生活の質)向上
完治を目指すよりも、できるだけ穏やかに過ごせるよう、継続的な治療とケアが求められます。
慢性腎臓病の犬猫と向き合う日々のリアルな背景紹介

慢性腎臓病と診断された犬や猫と暮らす飼い主にとって、日々のケアは「治す」ことよりも「進行を抑える」ことが大切になります。
例えば、毎日の食事管理や水分摂取への配慮、定期的な血液・尿検査、必要に応じた点滴など、生活の一部として医療的対応を行う必要があります。
また、体調の変化に敏感になることで早期の異変に気づけるようになり、飼い主とペットの絆も深まります。負担もありますが、「一日でも元気に過ごしてほしい」という思いが支えになります。
医学的背景
腎臓は老廃物排出だけでなく免疫系に深く関与
腎臓の主な役割は、血液中の老廃物や余分な水分を尿として排出することです。しかし近年、腎臓が免疫機能やホルモン分泌にも深く関わっていることが明らかになってきました。
腎臓は造血ホルモン(エリスロポエチン)の産生やビタミンDの活性化にも関与し、体全体の恒常性を維持する重要な臓器です。
そのため、腎臓が機能低下すると貧血や免疫力低下といった全身的な影響が現れることがあります。
腎不全や慢性腎臓病の進行に伴う免疫力低下や炎症増加のメカニズム解説
慢性腎臓病が進行すると、体内の毒素(尿毒素)が蓄積されることで慢性炎症を引き起こします。
また、腎臓で作られるエリスロポエチンの不足による貧血や、ビタミンDの活性低下による骨代謝異常など、免疫力を下げる原因が重なります。
結果として、感染症にかかりやすくなり、治療がさらに複雑になります。主なメカニズムは以下のとおりです。
- 尿毒素の蓄積による炎症性サイトカインの増加
- 酸化ストレスの上昇
- 腸内環境の悪化による免疫異常
- 慢性的な脱水による循環不良
参考論文:“The role of inflammation in CKD progression” (Nat Rev Nephrol, 2020)
参考論文:“Immune modulation in CKD” (Kidney Int, 2019)
獣医師の見解と現場での気づき
現場の獣医師たちは、腎臓病の兆候が現れる頃には病気がすでに進行しているケースが多いと指摘しています。
そのため、日頃の尿の量や飲水量の変化、元気・食欲の有無など、飼い主による「小さな気づき」がとても重要になります。
また、近年では腎臓病に対して食事やサプリメントでのアプローチが注目され、従来の治療法に加えて総合的な管理が求められています。治療のゴールは「完治」ではなく、「少しでも快適な日常を送ること」です。
現場の獣医師たちは、腎臓病の兆候が見られた時点で、すでに病気がある程度進行しているケースが多いと指摘しています。そのため、日々の飲水量や尿の変化、元気・食欲の有無といった、小さな変化への気づきが早期発見の鍵となります。
最近では、こうした日常的な観察に加えて、療法食や点滴といった基本的な治療のほか、手軽に取り入れられるサプリメントなどを活用した補助的なケアも注目されています。
「できることを少しでも増やしたい」という飼い主の思いに応える手段のひとつとして、免疫バランスや抗酸化をサポートする素材の活用が現場でも広がりを見せています。
その代表的な例として、特に今注目されているのが「フアイア」です。
参考:抗がん作用を獲得したフアイアのエビデンスについて | 新見正則医院【エビデンスに基づいた漢方治療】
参考:日本獣医フアイア研究会 Huai Qi Huang(フアイア)は軽度のIgA腎症患者のタンパク尿と血尿を改善する:前向きランダム化比較試験
注目素材:フアイアとは
フアイアは、中国で長年研究されてきた、きのこ由来の注目素材です。エンジュという木に共生する希少なきのこから見つかり、今では野生ではほとんど見られなくなっています。
現在は、このきのこの菌を培養することで、安全で安定したかたちで成分を取り出し、製品として活用できるようになりました。
フアイアは、免疫のバランスを整えたり、腎臓の働きをやさしく支えたりする力が期待されています。人の医療の現場では、1990年代からがん治療にも使われ始め、今では動物にも応用され、犬や猫の慢性的な体調のケアにも使われはじめています。
主成分の糖鎖TPG-1の抗酸化・免疫調整作用
フアイアの主成分である糖鎖TPG-1(特許成分)は、細胞間の情報伝達をスムーズにする働きがあり、免疫バランスの維持や細胞の修復促進、炎症抑制に寄与するとされています。
特に腎臓病で問題となる「酸化ストレス」を軽減し、慢性的なダメージの蓄積を和らげる働きが期待されています。
- 抗酸化作用により細胞の酸化ダメージを抑制
- 免疫系のバランスを整える
- 炎症性サイトカインの発現を調整
- 腎臓細胞の保護と修復をサポート
飼い主の声:使用者の実感
まとめ:犬猫の腎臓病を理解し、早期対応で健康を守ろう
症状に気づいたらすぐに動物病院へ
犬や猫の腎臓病は、初期には症状がほとんど見られないことが多いため、早期発見がとても重要です。
食欲不振や多飲多尿など、普段と異なる様子に気づいたらすぐに動物病院で診察を受けましょう。
また、7歳を超えたシニア期には年に2回以上の定期健診を受けることで、腎機能の異常を早期に捉えることができます。
予防と継続的なケアが何より大切
腎臓病を予防・管理するためには、水分摂取を促す環境づくりや、腎臓に負担の少ない療法食の導入、ストレスの少ない生活習慣の見直しがカギです。
また、気になるサプリメントや天然素材(例:フアイア)などの補助的手段も、獣医師の指導のもとで上手に取り入れるとよいでしょう。
継続的なケアによって、愛犬・愛猫の健やかな生活を支えることができます。
この記事の執筆者
nademo編集部
編集部
「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。
&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。
※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。
※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。
※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。
※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。
※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)
![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)










