愛犬の皮膚がなんだかベタベタしている…そんな悩みを抱える飼い主さんは多いのではないでしょうか。
皮膚のベタつきは、日常のケア不足だけでなく、皮膚病や内臓疾患のサインであることもあります。
本記事では、犬の皮膚がベタつく原因と考えられる病気、対処法や予防法まで、詳しく解説します。
この記事の結論
- 犬の皮膚のベタつきが続く場合は病院受診を検討する
- 乾燥による皮脂の過剰分泌がベタつきの原因になりやすい
- 一時的なベタつきと皮膚病は症状の有無で判断することになる
- 症状の重さや期間を観察し早めに対処することが重要
目次
犬の皮膚がベタつくのはなぜ?主な原因を解説

犬の皮膚がベタつく原因はさまざまで、日常生活の些細な要因から病気によるものまで幅広く考えられます。
特に、皮脂の分泌異常、皮膚の汚れや湿気、食事内容、アレルギー、ホルモン異常、内臓疾患などが関係しています。
これらの原因が複雑に絡み合って皮膚環境を悪化させることもあるため、見た目の変化だけで判断するのは難しく、専門的な視点が必要です。
皮膚の状態が長く続く、かゆみや臭いが伴う場合は早めの受診が大切です。
皮脂の過剰分泌によるベタつき
皮脂は犬の皮膚を保護する重要な成分ですが、過剰に分泌されると皮膚がベタつき、毛が脂っぽくなったり、臭いの原因にもなります。
特に「脂漏症(しろうしょう)」という皮膚疾患では、皮脂の量が異常に増え、皮膚がべたついてフケやかゆみを伴います。主な原因は以下の通りです。
- 遺伝的な体質(特定犬種に多い)
- シャンプー不足や洗いすぎ
- 高温多湿の環境
適切なシャンプーの選択と定期的な皮膚ケアが、ベタつきの改善に効果的です。
皮膚の汚れ・ホコリ・汗によるもの
犬は外での散歩や遊びを通して、皮膚や被毛にホコリ・花粉・汚れなどが付着します。これらが皮脂や汗と混ざることで、皮膚がベタつきやすくなります。
特に被毛の長い犬種や、皮膚の通気性が悪い部位(脇や首周りなど)は、汚れがたまりやすく注意が必要です。
対策としては、
- 定期的なブラッシングで汚れを除去
- 散歩後はぬるま湯で軽く洗い流す
- 通気性の良いハーネスや服の着用
など、日々のケアがベタつき予防に効果を発揮します。
食生活や栄養バランスの乱れ
食事の内容は、犬の皮膚状態と密接に関わっています。脂肪分の多いフードや、栄養バランスの偏った食事を続けていると、皮脂分泌が活発になり、皮膚がベタつきやすくなります。
特に、オメガ6系脂肪酸の過剰摂取は皮脂分泌を促進する可能性があります。
理想的な栄養バランスの例
| 栄養素 | 皮膚への効果 |
|---|---|
| オメガ3脂肪酸 | 炎症を抑え、皮膚を健康に保つ |
| ビタミンA | 皮膚の再生をサポート |
| 亜鉛 | 皮膚と被毛の健康維持に必要 |
栄養バランスの見直しは、皮膚環境の改善にもつながります。
ホルモン異常や内臓疾患が原因の場合
犬の皮膚のベタつきは、内臓疾患やホルモンバランスの異常によって引き起こされることもあります。特に以下の疾患に注意が必要です。
- 甲状腺機能低下症:皮膚が乾燥とベタつきを繰り返し、被毛も薄くなる
- クッシング症候群:皮脂分泌が活発になり、独特の臭いが発生
- 肝臓・腎臓の機能低下:体内毒素の排出がうまくいかず皮膚に異常が出る
このような場合、見た目のケアだけでは改善せず、根本的な治療が必要になります。気になる症状があれば、血液検査などの精密診断を受けましょう。
犬の皮膚のベタつきに関係する主な皮膚病
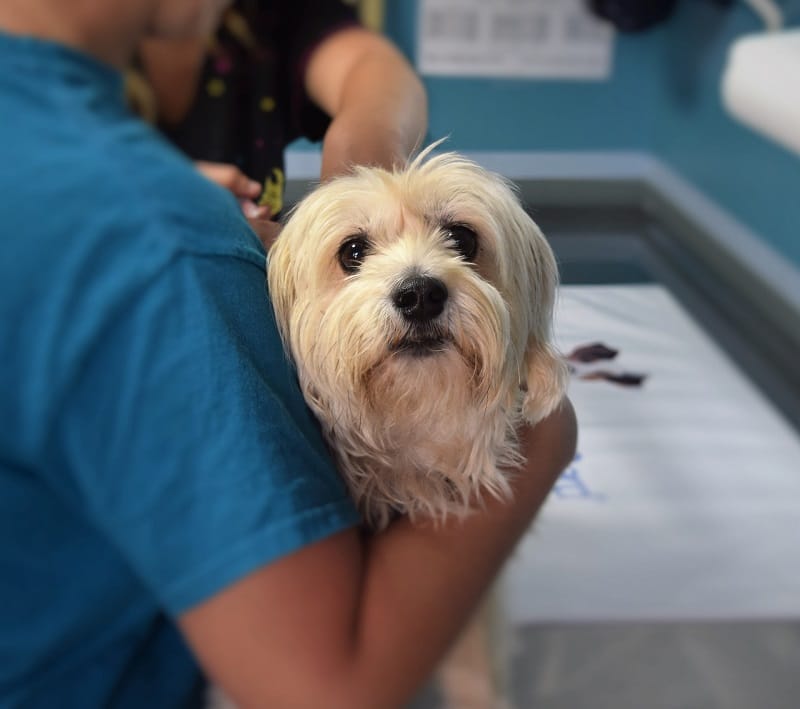
犬の皮膚がベタつく症状は、さまざまな皮膚病のサインであることが多く、特に「脂漏症」「マラセチア皮膚炎」「アトピー性皮膚炎」が代表的です。
これらは単なる汚れとは異なり、皮脂の分泌異常や菌の異常増殖、免疫反応などが原因で起こります。
症状が悪化すると、強い臭いや脱毛、赤み、かゆみを伴うことも。慢性化を防ぐためにも、早期発見・治療が重要です。
脂漏症とは
脂漏症(しろうしょう)とは、皮膚の新陳代謝に異常が起こり、過剰な皮脂や角質が分泌されることでベタつきやフケが発生する皮膚疾患です。
体質的に皮脂の分泌が多い犬種に多く、皮膚の見た目に明らかな異常が出やすいのが特徴です。
臭いが強くなる、皮膚が赤くなる、痒がるなどの症状も見られます。早期に対応することで、症状の悪化を防ぐことができます。
乾性脂漏と湿性脂漏の違い
脂漏症には「乾性脂漏(ドライタイプ)」と「湿性脂漏(オイリータイプ)」の2種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 乾性脂漏 | フケが多く乾燥気味、ベタつきは少なめ |
| 湿性脂漏 | 皮膚がベタつき、強い臭いや赤みが出やすい |
湿性脂漏は皮膚がべたついて毛が束になりやすく、細菌やマラセチアの繁殖も引き起こしやすいのが難点です。適切なシャンプーや内科的治療が必要です。
脂漏症の主な原因
脂漏症の原因は1つではなく、先天性・後天性のさまざまな要因が関係しています。主な原因は以下の通りです。
- 遺伝的な体質(コッカー・スパニエル、シー・ズーなど)
- 食事や栄養バランスの乱れ
- 内分泌疾患(甲状腺機能低下など)
- 不適切なシャンプーや過度な洗浄
- マラセチアなどの常在菌の異常増殖
原因に応じたケアと治療が必要なため、自己判断ではなく、獣医師による診断が大切です。
マラセチア皮膚炎とは
マラセチア皮膚炎は、マラセチアという常在酵母菌が異常増殖することで発症する皮膚病です。
特に皮脂の多い耳の内側、脇、股などに発症しやすく、皮膚のベタつき、強い臭い、赤み、かゆみなどが現れます。脂漏症や免疫力の低下、湿気の多い環境が引き金になることもあります。
適切な薬用シャンプーや抗真菌薬での治療が効果的です。
マラセチア菌の特徴と増殖の条件
マラセチア菌は皮膚に常在する酵母菌で、健康な状態では問題を起こしません。しかし以下のような環境では異常繁殖しやすくなります。
- 皮脂の分泌が多い
- 湿度や温度が高い
- 免疫機能が低下している
- 皮膚が傷ついている
特に湿気の多い季節や、脂漏症と併発した場合は急速に増殖し、皮膚炎を悪化させるリスクが高まります。
かゆみ・臭いなどの症状
皮膚のベタつきとともに現れる「かゆみ」や「臭い」は、皮膚病を見分ける大きなサインです。以下のような症状がある場合は、皮膚炎を疑うべきです。
- 皮膚を頻繁に舐める、かく
- 体臭が以前より強くなった
- 皮膚が赤く、ベタついて毛が束になる
- 触ると脂っぽく、湿った感じがする
これらの症状が続く場合、単なる汚れではなく、皮膚病の可能性が高いので、早めに動物病院を受診しましょう。
アトピー性皮膚炎・アレルギーによる皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、遺伝的な体質によりアレルゲン(ハウスダスト、花粉、食物など)に対して過敏に反応し、慢性的なかゆみや赤み、ベタつきが現れる病気です。
皮膚が炎症を起こし、二次的に脂漏症やマラセチア皮膚炎を併発することもあります。
完全な治癒は難しいこともありますが、アレルゲンの特定と適切な環境整備、薬の投与などで症状のコントロールは可能です。
内臓疾患(肝臓・甲状腺など)と皮膚症状の関係
犬の皮膚の異常は、内臓の病気と密接に関係している場合があります。特に以下の疾患は、皮脂分泌の異常を引き起こすことがあります。
| 疾患名 | 皮膚への影響 |
|---|---|
| 甲状腺機能低下症 | 皮膚の乾燥やベタつき、脱毛、色素沈着 |
| クッシング症候群 | 脂っぽい皮膚、薄毛、腹部のたるみ |
| 肝機能障害 | 皮膚のかゆみ、乾燥、色の変化 |
皮膚だけでなく、全身の健康状態をチェックし、必要に応じて血液検査や内科的治療が求められます。
犬の皮膚のベタつきに気づいたら何をすべき?

犬の皮膚がいつもと違ってベタついていると感じたら、まずは冷静に観察しましょう。
皮脂の過剰分泌や湿った手触り、独特の臭いがある場合、皮膚トラブルのサインである可能性があります。
軽度であれば、シャンプーや生活環境の見直しで改善することもありますが、長引く場合や、かゆみ・脱毛・赤みなどが併発している場合は、早めの受診が大切です。
症状の進行度や変化を見逃さず、愛犬の状態を日々チェックしましょう。
セルフチェックポイントと注意点
犬の皮膚のベタつきに気づいたとき、自宅で確認すべきポイントは以下の通りです。
- 皮膚の状態:赤み、フケ、ただれがないか
- 臭い:いつもより強い体臭がないか
- かゆみ:頻繁に掻く、舐める、こすりつける行動があるか
- 被毛の様子:毛が束になっている、べたついている部分があるか
- 行動の変化:元気がない、眠りが浅いなど体調不良の兆し
チェック時には無理に触らず、愛犬のストレスにならないよう優しく行いましょう。気になる点があれば、記録しておくと診察時に役立ちます。
動物病院を受診するタイミング
皮膚のベタつきが以下のような症状を伴う場合、早めに動物病院を受診することをおすすめします。
- かゆみや赤み、フケなどの異常が見られる
- 数日経っても改善せず、悪化している
- 部分的に毛が抜けている
- 明らかな臭いや皮膚の変色がある
- 食欲や元気がないなど、体調の変化も見られる
これらの症状は、脂漏症やマラセチア皮膚炎、ホルモン異常などの疾患が原因の可能性もあるため、早期に獣医師の判断を仰ぐことが重要です。
診察時に伝えるべき情報と準備
動物病院でスムーズに診察を受けるためには、飼い主からの正確な情報提供が重要です。以下の点をメモしておくと診察がスムーズになります。
- 皮膚のベタつきに気づいた日・頻度
- 併発している症状(かゆみ、赤み、臭いなど)
- 使用中のフードやおやつ、サプリメント
- 最近のシャンプーやスキンケアの内容
- 過去の皮膚トラブルや持病の有無
また、皮膚の状態をスマホで撮影しておくと、診察時に役立つこともあります。できる限り詳細な情報を伝えることで、適切な診断と治療方針の決定に繋がります。
犬の皮膚のベタつき対策と予防法

犬の皮膚のベタつきを予防・改善するには、日常的なケアと生活環境の見直しが欠かせません。
シャンプーやスキンケアの方法はもちろん、食事やサプリメントによる内側からのケア、そしてストレス管理も大切なポイントです。
皮膚トラブルの原因は多岐にわたるため、愛犬の体質や症状に合わせて総合的にアプローチすることが、ベタつきの根本的な改善につながります。継続的なケアが健康な皮膚を保つ鍵です。
シャンプーの頻度と選び方
犬の皮膚の状態に合わせたシャンプー選びと適切な頻度が重要です。
脂っぽさが強い場合でも洗いすぎは逆効果になることがあります。目安としては以下の通りです。
| 皮膚の状態 | シャンプー頻度 |
|---|---|
| 健康な皮膚 | 3~4週間に1回程度 |
| 脂漏傾向がある | 1~2週間に1回(獣医の指示に従う) |
低刺激で保湿効果のあるシャンプーや、皮脂バランスを整える成分が含まれた製品を選ぶとよいでしょう。
香料やアルコールを含む製品は避け、肌にやさしいものを選びましょう。
皮膚トラブル用の薬用シャンプー
皮膚のベタつきがある場合、一般的なシャンプーでは効果が不十分なこともあります。
獣医師に相談のうえ、薬用シャンプーの使用がすすめられるケースも少なくありません。以下のようなタイプがあります。
- 抗菌タイプ:細菌やマラセチアの増殖を抑える
- 抗脂漏タイプ:過剰な皮脂を取り除き皮膚を清潔に保つ
- 保湿・低刺激タイプ:皮膚バリアの再生をサポート
使用頻度や洗い方を誤ると逆効果になることもあるため、獣医師の指導のもとで使用しましょう。
食事・サプリメントでの内側からのケア
皮膚の健康は、外側からのケアだけでなく、内側からのサポートも大切です。特に以下の栄養素は皮膚の保湿力やバリア機能に関係しています。
- オメガ3脂肪酸(EPA・DHA):炎症の抑制や皮膚の潤いを保つ
- ビタミンE・ビタミンA:皮膚の再生や抗酸化作用
- 亜鉛:皮膚細胞の修復をサポート
皮膚ケアを目的としたサプリメントも多く市販されていますが、過剰摂取を防ぐために、必ず獣医師と相談して導入しましょう。
日常のスキンケアと清潔な生活環境の維持
日々のスキンケアでは、散歩後の足拭きや汚れやすい部分のこまめな拭き取りが効果的です。
また、犬の寝具やケージはこまめに洗濯し、皮脂や雑菌がたまらないよう清潔を保ちましょう。
加えて、部屋の換気や湿度管理も大切です。ジメジメした環境は皮膚病菌の繁殖を助けてしまいます。エアコンや除湿機を活用し、過度な乾燥や湿気を避けましょう。
ストレスを減らす生活環境の見直し
犬の皮膚の状態は、ストレスとも密接に関係しています。ストレスを受けると免疫力が低下し、皮膚のバリア機能も弱まります。以下のようなポイントを見直してみましょう。
- 十分な運動時間を確保する
- 急な生活環境の変化を避ける
- 落ち着ける場所(寝床やハウス)を整える
- 飼い主とのコミュニケーション時間を増やす
精神的に安定した暮らしを送ることが、皮膚の健康にも良い影響を与えます。
犬の皮膚のベタつきに関するよくある質問(FAQ)
犬の皮膚がベタつくだけで病院に行くべき?
皮膚のベタつきが軽度で一時的なものであれば、すぐに動物病院を受診する必要はありません。ただし、以下のような症状が伴う場合は、早めの受診をおすすめします。
- かゆみや赤み、湿疹などの皮膚炎症状がある
- 強い臭い、脱毛、フケの増加などが見られる
- ベタつきが数日~1週間以上続いている
- 元気がない、食欲不振など全身状態の変化がある
犬は言葉で不調を訴えられないため、皮膚の異常が全身疾患のサインであることもあります。迷ったときは、電話で相談だけでもしてみると安心です。
犬の皮膚が乾燥しているのにベタつくのはなぜ?
一見すると矛盾しているように思える「乾燥しているのに皮膚がベタつく」状態は、皮膚のバリア機能が低下しているサインかもしれません。
乾燥によって皮膚が外部刺激に弱くなり、体が過剰に皮脂を分泌してしまうことで、逆にベタつきが発生するのです。また、以下のような原因も考えられます。
- シャンプーのしすぎによる皮脂バランスの乱れ
- 栄養不足や水分不足
- アレルギーや軽度の皮膚炎の初期症状
このような状態では、保湿ケアや食事の見直しが有効な場合もあります。必要に応じて獣医師に相談しましょう。
犬の皮膚の一時的なベタつきと慢性的な皮膚病の見分け方は?
一時的な皮膚のベタつきと、慢性的な皮膚病によるベタつきには、いくつかの見分けるポイントがあります。
| 見分けポイント | 一時的なベタつき | 慢性的な皮膚病 |
|---|---|---|
| 持続期間 | 数日程度で自然に治まる | 数週間~月単位で続く |
| 付随する症状 | 特に見られない、または軽度の臭いなど | かゆみ、脱毛、赤み、フケ、湿疹など多数 |
| 皮膚の変化 | 目立った異常はなし | 色素沈着、厚み、じゅくじゅく感あり |
慢性的な症状は、脂漏症やマラセチア皮膚炎、ホルモン異常などの皮膚疾患が関係している可能性が高いため、早めに専門的な診断を受けることが大切です。
この記事の執筆者
nademo編集部
編集部
「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。
&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。
※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。
※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。
※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。
※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。
※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)
![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)






