「愛犬の皮膚がなんだか赤い気がする…」「もしかして病気?」と心配になっていませんか?
犬の皮膚の赤みは、かゆみを伴ったり、ただれてしまったりと、愛犬にとってつらい症状のひとつです。原因はアレルギーや感染症など多岐にわたり、適切な対応が必要です。
この記事では、犬の皮膚が赤くなる主な原因や考えられる病気、自宅でできるケア方法、そして動物病院を受診するべき目安について詳しく解説します。愛犬の皮膚トラブルを早期に発見し、適切なケアをするために、ぜひこの記事を参考にしてください。
この記事の結論
- 犬の皮膚の赤みは、アレルギー、寄生虫、感染症など多様な原因がある
- 赤みが広がったり、強いかゆみや全身症状があれば、すぐに動物病院を受診する
- 定期的な皮膚チェック、適切なシャンプーと保湿、ノミ・ダニ予防、バランスの取れた食事が大事
- 飼い主さんの日々の注意深い観察と、異常に気づいた際の迅速な対応が何よりも重要
目次
犬の皮膚が赤くなる主な原因

愛犬の皮膚の赤みは、体のどこかに異常があるサインかもしれません。原因はひとつではなく、アレルギー、寄生虫、感染症、ホルモン異常、物理的な刺激など、多岐にわたります。
原因によって治療法が異なるため、赤みに気づいたら、かゆみやフケなど他の症状がないかもよく観察することが大切です。
考えられる主な原因としては、以下のようなものがあります。
- アレルギー性皮膚炎(食物、環境など)
- 外部寄生虫の寄生(ノミ、ダニなど)
- 細菌や真菌(カビ)の感染
- ホルモンバランスの異常
- 物理的な刺激や摩擦
これらの原因が複合的に関わっている場合もあります。正確な原因を知るためには、動物病院での診察が不可欠です。
アレルギー性皮膚炎について
アレルギー性皮膚炎は、犬の皮膚トラブルで非常に多い原因のひとつです。
本来は体を守るための免疫機能が、特定の物質に対して過剰に反応してしまうことで起こります。この過剰な免疫反応が皮膚に炎症を引き起こし、赤みやかゆみなどの症状が現れます。
遺伝的な素因を持つ犬種も多く、一度発症すると慢性化しやすい傾向があります。
アレルギー性皮膚炎は、主に「食物アレルギー」と「環境アレルギー(アトピー性皮膚炎)」に大別されます。
どちらも強いかゆみを伴うことが多く、犬が体を舐めたり掻いたりすることで皮膚が傷つき、さらに症状が悪化することもあります。正確な診断と継続的なケアが重要です。
食物アレルギーが原因の場合
食物アレルギーは、特定の食べ物に含まれるタンパク質などに対して免疫が過剰に反応することで起こります。
原因となることが多いのは、普段から食べているフードに含まれることの多い牛肉、鶏肉、乳製品、小麦などです。
皮膚の赤みやかゆみだけでなく、下痢や嘔吐といった消化器症状を伴うこともあります。診断には、原因の可能性のある食べ物を完全に除去し、症状が改善するかを確認する「除去食試験」が一般的に行われます。
原因が特定されたら、その成分を含まない療法食に切り替えるなど、厳格な食事管理が治療の中心となります。
環境アレルギー(アトピー性皮膚炎)が原因の場合
環境アレルギー、またはアトピー性皮膚炎と呼ばれるものは、花粉、ハウスダスト、ダニ、カビといった環境中のアレルゲンを吸い込んだり皮膚から吸収したりすることで起こるアレルギー反応です。
遺伝的な素因が関わることが多く、特定の季節に症状が出る場合(花粉など)と一年中症状が見られる場合があります。
耳、顔、脇、内股、指の間などが好発部位で、強いかゆみとそれに伴う皮膚の赤み、湿疹、脱毛などが主な症状です。診断にはアレルギー検査や、他の原因を除外していく方法が取られます。
治療はアレルゲンを避ける努力に加え、かゆみや炎症を抑える薬物療法、皮膚のバリア機能を保つスキンケアなどが組み合わせて行われます。
根気強いケアが必要となることが多い疾患です。
外部寄生虫(ノミ・ダニ)の寄生
ノミやダニといった外部寄生虫の寄生も、皮膚の赤みやかゆみの一般的な原因です。
特にノミの唾液に対するアレルギー反応である「ノミ刺咬症アレルギー性皮膚炎」は、一匹のノミに刺されただけでも非常に強いかゆみと広範囲の赤みを引き起こすことがあります。マダニに咬まれた箇所が赤く腫れたり、ヒゼンダニ(疥癬)が寄生して激しいかゆみや皮膚炎を起こすこともあります。
動物病院で寄生虫の種類を特定し、適切な駆虫薬を投与することが重要です。
また、寄生虫の予防は年間を通して行うことが、皮膚トラブルを防ぐ上で最も効果的な対策となります。定期的な予防薬の投与を忘れずに行いましょう。
細菌や真菌(カビ)の感染
健康な犬の皮膚にも常在している細菌(ブドウ球菌など)や真菌(マラセチアなど)が、皮膚のバリア機能の低下や免疫力の低下、他の皮膚疾患などによって異常に増殖することで感染が起こり、皮膚の赤みや炎症を引き起こします。
細菌感染では、赤み、かゆみに加えて、膿を持ったぶつぶつ(膿疱)やフケ、かさぶたが見られることがあります。真菌(マラセチア)感染では、皮膚がベタつき、強いニオイを伴う赤みやフケ、色素沈着が見られることが多いです。
診断には皮膚の表面をこすったり、被毛を抜いて顕微鏡で観察する検査などが行われます。
治療は原因菌に合わせた抗生物質や抗真菌薬の内服や外用薬、薬用シャンプーによる洗浄などが行われます。
ホルモンバランスの異常
ホルモンバランスの異常によっても皮膚のトラブルが起こり、赤みが見られることがあります。代表的なものに、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などがあります。
甲状腺機能低下症では、皮膚の新陳代謝が低下し、乾燥、脱毛、皮膚の厚み、そして二次的な皮膚感染による赤みなどが見られます。
副腎皮質機能亢進症では、皮膚が薄くなる、左右対称性の脱毛、色素沈着、皮膚の感染などが起こりやすくなります。
これらの疾患は見た目の皮膚症状だけでなく、元気がなくなる、体重が増える、水をよく飲むなどの全身症状を伴うことが多いです。
血液検査などでホルモン値を調べ、診断が確定すれば、ホルモン剤などで治療を行います。
物理的な刺激や摩擦
首輪やハーネスが体に合っていないことによる擦れ、硬い床での摩擦、特定の場所(特に足先など)を過剰に舐めたり噛んだりすることによる「舐性皮膚炎」も皮膚の赤みの原因となります。
また、植物や化学物質に触れたことによる接触性皮膚炎(かぶれ)や、シャンプーが体に合わないことも原因となることがあります。
これらの物理的な刺激や摩擦による赤みは、原因となっているものを取り除くことが最も重要です。
舐性皮膚炎の場合は、エリザベスカラーや包帯で物理的に舐めるのを防ぐ処置が必要となることもあります。
原因がはっきりしている場合は、比較的改善しやすいことが多いですが、慢性化すると治療に時間がかかる場合もあります。
犬の皮膚の赤み以外にチェックしたい症状

愛犬の皮膚に赤みを見つけたら、それ以外の症状がないかも注意深く観察することが病気の診断に繋がります。
赤みは皮膚トラブルの一症状であり、同時に現れる他のサインを見逃さないことが重要です。
チェックしたい主な症状は以下の通りです。
- かゆみや掻きむしる行動
- 脱毛やフケ、かさぶた
- 皮膚の厚みや色素沈着
- 嫌なニオイ
これらの症状を総合的に確認し、動物病院を受診する際に獣医師に詳しく伝えるようにしましょう。
強いかゆみや掻きむしり
皮膚の赤みとともにかゆみがある場合、愛犬は体を頻繁に舐めたり、噛んだり、床に擦り付けたりします。
あまりにも強いかゆみは犬にとって大きなストレスであり、睡眠不足や食欲不振につながることもあります。
また、掻きむしることで皮膚を傷つけ、そこから細菌などが感染して症状が悪化(二次感染)するリスクが高まります。
かゆみの程度は皮膚病の重症度を示す重要なサインのひとつです。
脱毛やフケ、かさぶたの有無
皮膚の炎症が続くと、被毛が抜けやすくなり脱毛が見られることがあります。
また、皮膚のターンオーバーが乱れることで、乾燥したフケや脂っぽいフケが出たり、傷口や湿疹がかさぶたになったりします。
これらの症状は、アレルギー、寄生虫、感染症など、さまざまな皮膚病で共通して見られますが、フケの質やかさぶたの状態などが診断の手がかりとなることもあります。
皮膚全体や特定の部位にこれらの症状がないかを確認しましょう。
皮膚の厚みや色素沈着の変化
慢性の皮膚炎が長期間続くと、皮膚が厚くゴワゴワとした質感になったり(苔癬化)、メラニン色素が増えて皮膚が黒ずんだり(色素沈着)することがあります。
これらは皮膚病が慢性化しているサインであり、すぐに治る状態ではないことを示唆します。
特に、脇や内股、お腹など摩擦が多い部分や、アレルギーで炎症が起きやすい部分に現れやすい傾向があります。
皮膚の色や質感に変化がないか、触って確認してみましょう。
嫌なニオイ(体臭)
健康な犬の皮膚にはほとんどニオイがありませんが、細菌や真菌(特にマラセチア)が異常に増殖すると、独特の嫌なニオイが発生することがあります。
脂っぽく、カビ臭い、あるいは酸っぱいようなニオイがすることが多く、特に皮膚の赤みやベタつきを伴う場合に顕著になります。
耳や皮膚のひだ、指の間など、蒸れやすい場所でニオイが強くなる傾向があります。
ニオイは皮膚感染症の重要なサインとなるため、愛犬の体を優しく撫でてニオイがないか確認するのも大切です。
犬の皮膚の赤み、自宅でできる応急処置とケア

愛犬の皮膚の赤みに気づいた際、動物病院に行く前に自宅でできる応急処置や、日頃からできるケアがあります。
これらのケアは症状の悪化を防ぎ、愛犬の不快感を和らげるのに役立ちますが、あくまで補助的な対応です。根本的な原因を特定し治療するためには、必ず動物病院を受診してください。
自宅でできるケアのポイントは以下の通りです。
- 患部を清潔に保つ
- 掻かせない工夫をする
- 皮膚の健康をサポートする
これらのケアを適切に行いながら、早めに獣医師の診察を受けることが大切です。
清潔を保つためのシャンプー選びと方法
皮膚を清潔に保つことは、皮膚の常在菌のバランスを整えたり、アレルゲンや汚れを取り除いたりする上で重要です。
しかし、洗いすぎたり、犬の皮膚に合わないシャンプーを使ったりすると、かえって皮膚のバリア機能を損ね、症状を悪化させる可能性があります。
犬用の低刺激シャンプーや、獣医師に推奨された薬用シャンプーを選び、皮膚を傷つけないように優しく洗い、しっかりとすすぎ、完全に乾かしてあげましょう。
シャンプーの頻度も皮膚の状態に合わせて調整が必要です。
保湿ケアの重要性
乾燥した皮膚はバリア機能が低下し、外部からの刺激やアレルゲンが侵入しやすくなります。特にアレルギー体質の犬や乾燥しやすい季節には、適切な保湿ケアが重要です。
保湿剤にはスプレータイプやローションタイプ、クリームタイプなどさまざまなものがあります。シャンプー後や普段のお手入れの際に、乾燥しやすい部分を中心に保湿剤を塗布することで、皮膚の潤いを保ち、健康な皮膚バリア機能を維持するサポートになります。
犬用に開発された安全性の高い製品を選びましょう。
食事内容の見直し
食事内容の見直しは、特に食物アレルギーが疑われる場合や、皮膚の健康を体の内側からサポートしたい場合に有効です。食物アレルギーの場合は、特定の原因食材を含まない療法食への切り替えが必要になります。
また、皮膚のバリア機能を高めるオメガ3脂肪酸などの必須脂肪酸や、皮膚の健康に必要なビタミン、ミネラルなどをバランス良く含む栄養バランスの取れた食事を与えることも重要です。
ただし、自己判断で大幅な食事変更を行う前に、必ず獣医師に相談し、愛犬に合った食事指導を受けるようにしてください。
こんな時はすぐに動物病院へ!犬の皮膚の赤みの受診目安

犬の皮膚の赤みに気づいたら、様子を見ることもありますが、症状によってはすぐに動物病院を受診する必要があります。
特に以下のような症状が見られる場合は、迷わず動物病院に連絡し、診察を受けるようにしてください。早期の対応が愛犬の苦痛を和らげ、病気の進行を防ぐために非常に重要です。
- 赤みが急速に広がっている、ただれている
- 強いかゆみで日常生活に支障が出ている
- 元気がない、食欲不振などの全身症状がある
これらのサインを見逃さず、迅速な対応を心がけましょう。
赤みが急速に広がっている、ただれている
皮膚の赤みが数日のうちに広範囲に広がったり、皮膚の表面が剥がれてただれたり、ジュクジュクした状態になっている場合は危険なサインです。
これは炎症が急速に進行しているか、細菌や真菌による二次感染がひどくなっている可能性が高いことを示します。
見た目にも重症な状態であり、放置すると全身状態にも影響を及ぼす可能性があります。早急に動物病院で適切な処置と治療を受ける必要があります。
強いかゆみで日常生活に支障が出ている
皮膚の赤みにかゆみが伴うことは多いですが、そのかゆみがあまりにも強く、愛犬が夜眠れなかったり、食事中も体を掻きむしったり、遊ぶことへの関心を失ったりしている場合は、日常生活に支障が出ているサインです。
激しいかゆみは犬にとって大きなストレスであり、QOL(生活の質)を著しく低下させます。また、掻き壊しによる二次感染のリスクも高まります。
犬を苦痛から解放するためにも、早急にかゆみを抑える治療が必要です。
元気がない、食欲不振などの全身症状がある
皮膚の赤みという局所的な症状だけでなく、普段よりも元気がなくぐったりしている、好きなものも食べない、熱がある、呼吸が荒いといった全身的な症状が見られる場合は、皮膚の炎症が全身に波及しているか、あるいは皮膚症状の背景に内臓疾患など別の重篤な病気が隠れている可能性があります。
これらの全身症状は、体のどこかに深刻な問題が起きているサインです。皮膚の赤みと合わせてこのような症状が見られる場合は、一刻も早く動物病院で精密検査を受け、適切な治療を開始することが非常に重要です。
犬の皮膚の赤みの動物病院での検査と治療法
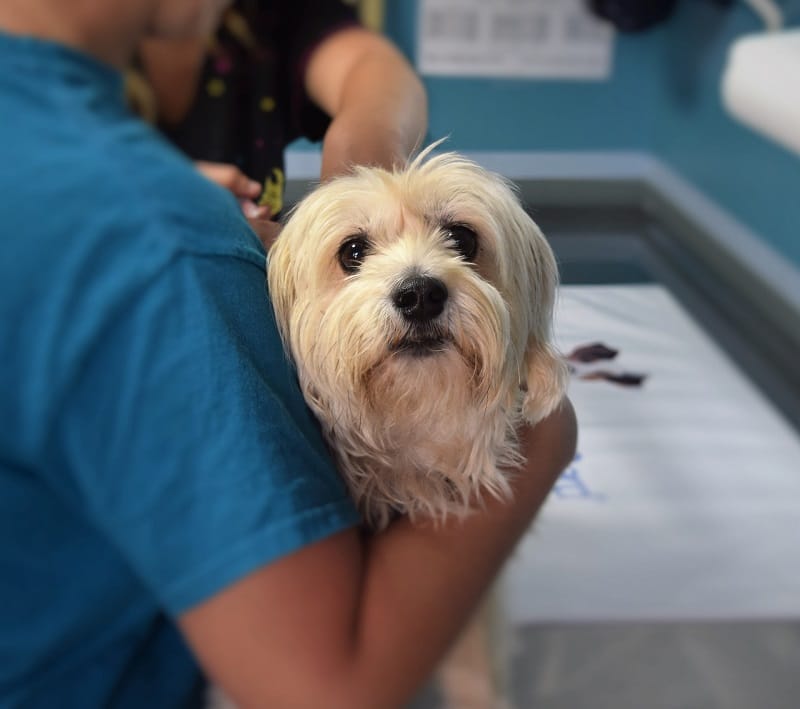
愛犬の皮膚の赤みの原因を正確に特定し、適切な治療を行うためには、動物病院での専門的な診察と検査が不可欠です。
獣医師は皮膚の状態を詳しく観察し、必要に応じてさまざまな検査を行います。診断に基づいて、原因に合わせた薬物療法や、スキンケアなどを組み合わせて治療を進めていきます。
自己判断でのケアには限界があるため、必ず獣医師に相談しましょう。
原因を特定するための各種検査
皮膚の赤みの原因は多岐にわたるため、正確な診断にはさまざまな検査が行われます。
- 視診・触診:皮膚の状態や分布を詳しく観察し、触って確認します。
- 皮膚掻爬検査:皮膚の表面を軽くこすり、ダニなどがいないか顕微鏡で調べます。
- セロハンテープ検査:皮膚にセロハンテープを貼り付け、菌や細胞などを採取して調べます。
- 真菌培養検査:カビの一種である真菌がいないか培養して調べます。
- 細菌培養検査:細菌感染が疑われる場合に、原因菌を特定し有効な抗生剤を調べます。
- アレルギー検査:血液や皮膚テストで、アレルギーの原因物質を特定します。
- 血液検査:ホルモン異常や全身状態を調べます。
これらの検査結果から、赤みの根本原因を特定し、最適な治療法を決定します。
薬物療法(内服薬、外用薬)
皮膚の赤みや炎症、かゆみを抑えるために、さまざまな薬が使用されます。
- かゆみ止め・抗炎症薬:ステロイド剤や、かゆみを特異的に抑える新しいタイプの薬(アポキル、サイトポイントなど)が内服薬や注射で用いられます。
- 抗生剤・抗真菌剤:細菌や真菌の感染がある場合に、原因菌に有効な内服薬や外用薬が処方されます。
- 外用薬:炎症を抑えるクリームや、殺菌・抗菌作用のある塗り薬などを患部に直接塗布します。
症状の程度や原因に合わせて、これらの薬が単独または組み合わせて使用されます。
薬用シャンプーやサプリメントによるケア
薬物療法と並行して、皮膚の健康をサポートするために薬用シャンプーやサプリメントが推奨されることがあります。
薬用シャンプーは、皮膚の表面についたアレルゲンや汚れを洗い流したり、特定の細菌や真菌の増殖を抑えたりする効果があります。
皮膚の状態に合わせて、保湿成分を含むものや、殺菌成分を含むものなどさまざまな種類があります。
また、オメガ3脂肪酸などの必須脂肪酸を含むサプリメントは、皮膚のバリア機能を内側から強化し、炎症を抑える効果が期待できます。
犬の皮膚トラブルを予防するために

愛犬の皮膚の赤みを含むさまざまな皮膚トラブルは、日頃からの適切なケアと予防によって、発生するリスクを減らすことができます。
毎日愛犬と触れ合う中で皮膚の状態をチェックしたり、清潔を保ったりすることが、健康な皮膚を維持するために非常に重要です。
皮膚トラブルを未然に防ぎ、愛犬が快適に過ごせるように、以下の予防策を実践しましょう。
日頃の皮膚チェックとブラッシング
毎日のスキンシップの時間などを利用して、愛犬の皮膚全体を優しく触って観察しましょう。
特に、耳の中、口の周り、脇の下、内股、指の間、お腹などを注意深くチェックし、赤みやベタつき、フケ、ニオイなどの異常がないか確認してください。早期に異常を発見できれば、症状が軽いうちに対応できます。
また、定期的なブラッシングは、被毛のもつれを防ぎ、皮膚の通気性を良くし、血行を促進する効果もあります。
適切なシャンプーと保湿ケアの実践
犬の皮膚を健康に保つためには、清潔を保つことが重要ですが、洗いすぎや犬に合わないシャンプーは逆効果です。
犬種や皮膚の状態に適した低刺激性のシャンプーを選び、優しく丁寧に洗ってください。シャンプー後はしっかりすすぎ、完全に乾かすことも大切です。
また、皮膚の乾燥はバリア機能を低下させるため、シャンプー後や乾燥が気になる際には、犬用の保湿剤を使って保湿ケアを行うことを習慣にしましょう。
ノミ・ダニ予防薬の定期的な投与
ノミやダニは、皮膚のかゆみや赤み、アレルギー性皮膚炎の大きな原因となります。
これらの外部寄生虫から愛犬を守るためには、予防薬の定期的な投与が不可欠です。動物病院で処方されるスポットタイプや飲み薬など、さまざまな種類の予防薬がありますので、獣医師に相談して愛犬に合ったものを選び、指示された期間を守って一年を通して投与しましょう。
予防を徹底することが、皮膚トラブルだけでなく、寄生虫が媒介する病気の予防にも繋がります。
バランスの取れた食事管理
健康な皮膚と被毛は、体の内側で作られます。そのため、バランスの取れた質の良い食事を与えることは、皮膚トラブルの予防において非常に重要です。
特に、皮膚のバリア機能を高め、炎症を抑える効果が期待できるオメガ3脂肪酸などの必須脂肪酸を十分に摂取できるフードを選ぶと良いでしょう。
また、肥満は皮膚のひだに炎症を起こしやすくするため、適切な体重を維持することも大切です。
愛犬の健康状態に合わせた食事について、迷ったら獣医師やペット栄養管理士に相談しましょう。
まとめ|犬の皮膚の赤みに気づいたら早期対応を
愛犬の皮膚の赤みは、さまざまな原因で起こりうる皮膚トラブルのサインです。
アレルギー、寄生虫、感染症など、原因によって治療法は異なります。赤み以外にかゆみや脱毛、ニオイなどの症状がないかもよく観察し、少しでも気になる症状があれば、迷わず動物病院を受診しましょう。
早期に原因を特定し、適切な治療を開始することが、愛犬のつらい症状を和らげ、慢性化を防ぐために最も重要です。
日頃からの皮膚チェックや適切なスキンケア、予防を実践し、大切な愛犬の皮膚の健康を守ってあげてください。
この記事の執筆者
nademo編集部
編集部
「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。
&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。
※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。
※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。
※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。
※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。
※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)
![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)















