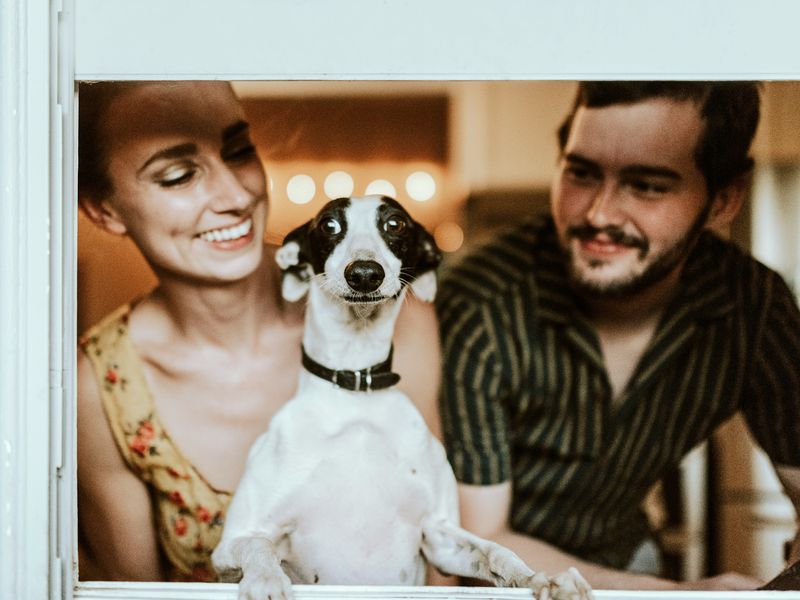「犬の放し飼いは自由でのびのびしていて良さそう」と思う飼い主もいるかもしれませんが、実は重大なトラブルや法律違反につながる恐れがあります。
この記事では、犬の放し飼いに関する法律やリスク、安全な飼育方法までを詳しく紹介します。
犬と人、どちらにも優しい飼い方を考えるきっかけになれば幸いです。
この記事の結論
- 犬の放し飼いは法律違反となる場合が多く注意が必要
- ドッグランや専用施設の活用で安全に自由を確保
- 庭で遊ばせる際は脱走防止や近隣への配慮が必須
- GPSやしつけ訓練で安全性と管理能力を高めることが重要
目次
犬の放し飼いは違法?基本知識を押さえよう

犬の放し飼いは一見、自由でストレスのない飼育方法のように思われがちですが、実際には多くのリスクと法的責任が伴います。
多くの自治体では、公共の場での犬の放し飼いを禁止しており、違反すると罰金や注意喚起の対象になります。
飼い主には、犬の行動を常に管理する「所有者責任」が課せられており、「うちの子は大丈夫」と思っていても、他人に危害を加えれば重大な問題となります。
まずは放し飼いの基本知識と法的立場を理解し、安全な飼育方法を選ぶことが重要です。
放し飼いとは?リードなしで自由に動ける状態の意味
「放し飼い」とは、リード(引き綱)をつけずに犬を自由に歩かせたり走らせたりする状態を指します。主に以下のような状況が該当します。
- 公園や道路など公共の場所でリードなしで散歩する
- 自宅の敷地外に犬を自由に出入りさせる
- ノーリードで犬を遊ばせる場所で管理が不十分な状態
このような放し飼いは、犬にとっては自由に見えるかもしれませんが、思わぬ事故やトラブルを招く原因となることが多く、法律上も問題視されています。
放し飼いは法律違反になる?各都道府県の条例や動物愛護法について
日本では、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」により、犬の適正な飼育が義務付けられています。
加えて、各都道府県や市町村の動物取扱条例においても、放し飼いは明確に禁止されているケースが多数あります。
| 地域 | 放し飼いに関する規定 |
|---|---|
| 東京都 | 公共の場でのリード未装着は禁止 |
| 大阪府 | 犬の逸走防止義務あり |
| 福岡市 | リードまたは柵による拘束が義務 |
また、事故やトラブルが発生した場合、民法709条(不法行為)により損害賠償責任を問われることも。飼い主は法的リスクを十分に理解しておく必要があります。
参考:環境省 動物愛護管理法
放し飼いに関する実際のトラブル・事故例
犬の放し飼いによるトラブルは実際に多数報告されており、ニュースや行政の注意喚起でもたびたび話題になります。以下は代表的な事例です。
- 放し飼いの犬が通行人に飛びかかりケガを負わせた
- ノーリードで散歩中、他の犬とケンカになり相手を傷つけた
- 公園で自由に遊ばせていた犬が道路に飛び出し交通事故に
これらのトラブルは、被害者の心身に影響を与えるだけでなく、飼い主にも経済的・社会的な責任が及びます。「自分の犬は大人しいから大丈夫」と思っても、予想外の行動をするのが動物です。
犬の放し飼いが抱えるリスクとは

放し飼いには、犬自身だけでなく周囲にも大きなリスクがあります。代表的なものを挙げると以下のようなものがあります。
- 人への咬傷や恐怖心を与える可能性
- 他の動物・犬とのケンカ
- 車との接触事故や迷子
- 感染症の拡大(ワクチン未接種の犬など)
飼い主の責任が問われるケースが多く、犬の命を守るという観点からも放し飼いは避けるべきです。犬との生活を守るためには、飼い主による適切な管理が不可欠です。
人への咬傷事故や恐怖心を与えるリスク
放し飼いにされた犬が、通行人や子どもに飛びかかったり吠えたりしてしまうと、それだけで大きな恐怖を与えることになります。
咬傷事故に発展すれば、被害者の治療費はもちろん、精神的な損害賠償も求められる可能性があります。
- 小さな子どもが転倒・ケガを負う
- 高齢者が驚いて転倒
- トラウマになり動物嫌いになる
犬をよく知っている飼い主には無害に見える行動でも、第三者には恐怖に映ることがあります。
犬自身が交通事故や迷子になる可能性
放し飼いは犬自身の命を危険にさらす行為でもあります。リードをつけていない犬は、ちょっとした物音や動きに反応して道路に飛び出すことがあります。
また、遠くへ走ってしまい、帰り道が分からず迷子になるケースも少なくありません。
危険なケース例
- バイクや車に接触して命を落とす
- 迷子になって保健所に保護される
- 行方不明のまま見つからない
リードは命綱です。飼い主が目を離した隙に何が起こるか分からないため、必ず使用しましょう。
他の動物や犬とのトラブル
放し飼いの犬が他のペットや犬に近づき、攻撃的な行動を取ってしまうケースもあります。
相手の犬がリードにつながれていた場合、不公平な状況からケンカに発展しやすくなります。さらに、他の飼い主やペットへの恐怖心やストレスの原因にも。
主なトラブル例
- リード犬に飛びかかる
- 猫や小動物を追い回す
- 鳥などを捕まえてしまう
犬同士のトラブルでも、怪我を負わせれば責任は飼い主にあります。安心して共生するには、適切な管理が必要です。
犬の放し飼いの代替案!安全で自由に遊ばせる方法

犬に自由を与えたいと思うのは自然なことですが、放し飼いは法律や安全面で問題が多いため、代替方法を検討しましょう。
最も一般的なのがドッグランの活用です。他にも自宅の庭を安全に整備する方法や、ノーリードが許可されている専用エリアの利用があります。
こうした代替手段を選ぶことで、犬もストレスをためず、飼い主も安心して遊ばせることが可能になります。
ドッグランの活用法とマナー
ドッグランはノーリードで犬を遊ばせられる貴重な場所ですが、利用にはルールとマナーが必要です。以下のポイントを守りましょう。
- ワクチン接種証明の提示が必要な施設が多い
- 他の犬との相性を事前に観察する
- トラブルが起きそうな場合はリード着用に戻す
- フンの処理やマーキング対策は自己責任で行う
また、小型犬と大型犬のエリアが分かれている場合には、指定された場所を守ることも重要です。
ノーリード可能な専用施設・場所とは
日本では公共の場での放し飼いは原則禁止ですが、ノーリードが許可されている専用施設や私有地も存在します。例としては、以下のような場所があります。
| 場所 | 特徴 |
|---|---|
| 有料ドッグラン | 安全管理が徹底され、犬同士の交流も可能 |
| 犬用プライベートパーク | 会員制で予約制が多く、混雑を避けられる |
| ペット可キャンプ場 | 一部ノーリード可の区画あり(要確認) |
これらの場所でも、トラブル時の責任は飼い主にあることを忘れず、適切に管理しましょう。
庭で放し飼いにする場合の注意点
自宅の庭で犬を自由に遊ばせるのは比較的安全ですが、注意点も多くあります。
まず、脱走防止策が万全であることが前提です。さらに、庭にある植物や農薬などが犬にとって毒性を持つ場合もあるため、環境整備が重要です。
近隣に向かって吠えたりすることで騒音トラブルになることもあります。庭で放し飼いをする際も、「完全に安全な環境」とは言い切れない点を意識しましょう。
脱走防止のための柵・フェンスの設置
犬が庭から飛び出すのを防ぐためには、しっかりとした柵やフェンスの設置が必須です。以下の条件を満たすものが望ましいです。
- 高さ:小型犬で90cm以上、大型犬なら120cm以上
- 地面との隙間がない構造
- 錆びにくく丈夫な素材(メッシュ・アルミ製など)
特にジャンプ力のある犬種では高さだけでなく登れない構造にも配慮が必要です。設置後は、定期的な点検も忘れずに行いましょう。
周囲への配慮としつけの重要性
どんなに安全な環境を整えても、吠え声や飛び出しなどで近隣トラブルが起きれば放し飼いの代替案も成り立ちません。
そのためには、無駄吠えを抑えるしつけや呼び戻し訓練を確実に行うことが重要です。
また、近隣住民への配慮として、犬が外で遊んでいる時間帯や音量にも注意しましょう。飼い主のマナーとしつけが、犬の自由を守る鍵となります。
どうしても犬を放し飼いをしたいときの対策と心得

どうしても犬を自由にさせたい場合は、万全の準備と周囲への配慮が不可欠です。
無計画に放し飼いを行えば、事故や苦情の元になります。最低限、以下の対策を講じましょう。
- GPS付き首輪などの位置把握装置の導入
- 呼び戻しが確実にできる訓練
- 近隣住民への理解と協力の取り付け
犬の命を守るためにも、「自由=責任」であることを飼い主自身が深く理解する必要があります。
GPS付き首輪や見守りカメラの活用
放し飼いに近い環境で犬を自由にさせたい場合は、GPS付き首輪やペット用見守りカメラの活用が効果的です。
GPS機能により、万が一犬が脱走しても迅速に追跡・発見が可能となります。見守りカメラは、室内や庭での行動監視に役立ち、トラブルの兆候にもすぐ気付けます。
これらのアイテムは「目の届かない瞬間」を補う手段として非常に有効です。
しっかりとしたしつけと呼び戻し訓練
放し飼いやノーリードに近い環境では、犬が指示に従えるかどうかが非常に重要になります。特に「呼び戻し」は命を守る訓練です。
しつけのポイントは以下の通り
- 名前を呼んだら必ず戻る習慣づけ
- ご褒美を使ってポジティブな記憶を形成
- 他犬や人のいる環境でも指示が通るよう練習
継続的なトレーニングによって、いざという時に犬の命を守ることができます。
近隣住民とのトラブルを避けるためのコミュニケーション
犬を自由に遊ばせたいなら、近隣住民との良好な関係づくりも欠かせません。
特に庭で遊ばせる場合や、声が聞こえる環境下では事前に一言伝えておくと印象が良くなります。定期的に挨拶をし、何かあったときには迅速に対応する姿勢が信頼を生みます。
また、迷惑をかけた場合はすぐに謝罪と改善を行いましょう。トラブルを防ぐのは、犬のしつけだけでなく飼い主の姿勢も関係しています。
まとめ|犬も人も安心して暮らせる環境を
放し飼いは一見、犬にとって理想の自由な環境に思えるかもしれませんが、法律・マナー・安全面など、多くのリスクを伴います。
代替案を上手に活用し、しつけと設備の工夫、周囲との調和を心がけることで、犬も人も安心して暮らせる環境を実現できます。
飼い主としての責任を忘れず、愛犬との健全な暮らしを目指しましょう。
この記事の執筆者
nademo編集部
編集部
「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。
&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。
※ 当コンテンツで紹介する商品は、実際に社内で利用した経験と、ECサイトにおける売れ筋商品・口コミ・商品情報等を基にして、nademo編集部が独自にまとめています。
※ 本記事はnademoが独自に制作しており、メーカー等から商品提供を受けることもありますが、記事内容や紹介する商品の意思決定には一切関与していません。
※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。
※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。
※ 掲載している商品の順番に意図はなく、掲載の順番によってランク付けしているものではありません。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)
![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)